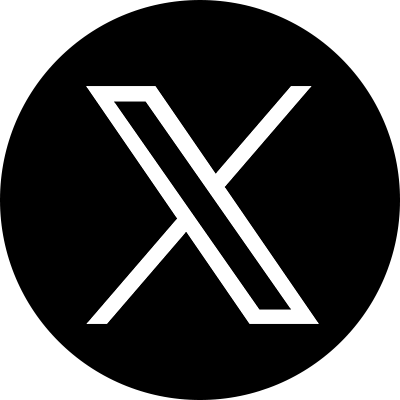企業や私生活でも生成AIの利用が浸透している一方で、
「生成AIを具体的に自分の業務に活用するイメージがわかない…」
「どうやって使えばいいの?」
といった疑問や課題を抱えている方もまだまだ多いのではないでしょうか。
このたびHakuhodo DY ONEでは、こうした疑問や課題をお持ちの方向けに、
生成AI活用基礎研修『生成AI BootCamp』を開催しました。
本記事では、『生成AI BootCamp』で実際に行ったセミナーとワークショップの内容をレポートします。
生成AI活用の基礎研修『生成AI BootCamp』とは
皆さまもご存じの通り、近年生成AIの利用は急速に拡大しています。若年層や一定数の企業では、生成AIの利用が当たり前、またAI活用による高いパフォーマンスが標準となってきているため、今後の「当たり前」の水準が上がっていくと考えられます。
こうした状況を受けて、Hakuhodo DY ONEでは、弊社内における生成AIの導入・活用推進に取り組んできた実績と、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告のノウハウを活かし、
生成AI活用の基礎研修『生成AI BootCamp』を開催しました!
本研修では、"生成AIを明日からの業務に活かす"をコンセプトとし、生成AIの基礎理解とプロンプト作成の実践ワークを通して、特に広告業務における生成AIの活用イメージを持つ、ということをゴールとしています。
先日開講した実際の研修では、生成AIの基礎や最新トピックス、ユースケースに関するセミナーのあと、実践ワークとしてChatGPTを活用したプロンプトレクチャーを行いました。
<プログラムの流れ>
生成AIの基礎セミナー~これまでの進化と生成AIに対する考え方~
セミナーでは生成AIの仕組みや最新トピックスを通して、生成AIの基礎に関する講義を行いました。また、生成AIの業務活用へのヒントを得ていただけるよう、生成AIのシンボリックユースケースを紹介し、企業内での活用方法を解説しました。
ここでは、生成AIの基礎講義の一部をご紹介します。
生成AIの進化
生成AIと言えばChatGPTを1番に思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
ChatGPTのチャット画面に指示内容をテキストで入力すれば、その指示に対してテキストで回答を返してくれる、というのが一般的な生成AIのイメージかもしれませんが、今の生成AIは、目が見え、耳が聞こえるように、圧倒的に進化しています。
従来のLLM(大規模言語モデル)では、テキストの処理・生成しかできませんでしたが、テキスト・画像・音声などの複数種類の情報を処理できるAIモデル、LMM(大規模マルチモーダルモデル)が登場したことで、画像からテキストを生成したり、逆にテキストから動画を生成したりなど、種類の異なる情報も一緒に処理・生成することが可能となりました。
では、最新の生成AI技術では何ができるのでしょうか?
最新の生成AI|AI検索エンジン『Felo』
『Felo』はSparticle社が、2024年7月にリリースした日本発の新しいAI検索エンジンです。
リサーチや情報の整理に優れているのはもちろん、スライド資料やマインドマップ、画像まで生成可能で、PowerPoint形式でプレゼンスライドを自動生成する機能があり、検索結果をもとに効率的な資料作成ができるという特徴があります。
『Felo』を活用すれば、競合他社のリサーチが簡易的に実施でき、調査した結果から資料を作成することができます。

AIエージェントの登場
2025年以降の生成AIにおいて重要なトピックとなるのが、「AIエージェント」の登場です。2025年はAIエージェント元年とも呼ばれています。
AIエージェントとは、人が設定した目標に対して、必要なデータを収集し、そのデータに基づいて自己決定タスクを決めながら目標を達成するためのプログラムのことです。
このAIエージェントの登場は、あらゆるビジネスに大きなインパクトを与えることが予想されます。詳細は以下の記事で紹介していますので、あわせてご一読ください。
>>AIエージェント元年の2025年 - マーケティング組織が直面する3つの論点
結局、生成AIとは何なのか?
生成AIはさまざまな進化を遂げていますが、生成AIがどのような仕組みになっているか、という基本的なことを押さえておくと、生成AIとは何かが理解しやすくなります。
言語の生成AIが行っていること・仕組みは、大雑把に言うと「続きにくるであろう単語を予測している(=もっともらしい文章を出しているだけ)」ということです。
この基本的な仕組みから生成AIの得意・不得意が見えてきます。以下の図にもあるように、生成AIはコンテンツ生成や情報提供、作業の効率化は得意ですが、正確性や感情理解、複雑な数値計算、倫理判断は苦手です。

生成AIへタスクを依頼、つまり指示をするときに重要となるのが、AIへの指示書であるプロンプトです。プロンプトをどのように書いていくかが生成AI活用のポイントと言えます。
ChatGPTを活用した実践ワークショップ~実際にプロンプトを作成してみよう~
セミナーで基礎を学んだ後は、実践的なワークショップを行い、段階的にプロンプトの作成方法を習得していきます。
お題ごとにプロンプトを作成し、そのプロンプトをChatGPTに入力するとどのような結果が出るのか、個人ワークをしていただきます。その後のグループワークでは、各自が作成したプロンプトの内容や回答結果を共有し、プロンプトに対する理解を深めます。
当日の研修では、各グループにHakuhodo DY ONEのAIコンサルタントがテーブルファシリテーターとしてフォローする形で進行しました。

プロンプト作成実践ワークショップの流れ
ワークショップでは、基礎編・初級編・中級編に分けてお題を設定し、効果的なプロンプトの作成方法を学んでいただきました。
基礎編では、ChatGPTへ簡単な指示をするところから始めます。今回のワークでは「理想の日本一周プランを考えてください」というお題で、制限限時間内にプロンプトを作成して回答を検証してもらいました。理想の回答をイメージし、それを言語化することで、より具体的な指示を出す練習を行います。
続いて、初級編・中級編では、プロンプトの構成要素を理解し、それらを活用することで、ChatGPTからの回答精度を高める方法を学んでいきます。今回は、ある商材の訴求軸を洗い出すプロンプトを作成するというワークを通して、実際に業務で活用いただける実践的なスキルを習得していただきました。
<グループワーク:各自で作成したプロンプトを共有している様子>
ワークショップ参加者の声
参加者に事後アンケートを実施したところ、実践ワークショップでは多くの方に生成AIを業務で活用するイメージを持っていただくことができ、大変好評いただきました!
以下参加者からの声を一部ご紹介します。
<参加者の声> ※アンケート内容を一部抜粋
- ChatGPTのプロンプト作成のコツが理解できた。
- 生成AIのトレンドからプロンプト作成の実践まで学ぶことができたので満足しております。
- 実際に動かしてみたり、手を動かす機会があり学べる機会となった。
- プロンプトの作成方法を学べたことが一番有意義だった
- 特に後半のワークショップが有意義でした。
- AIの全体的な話から、細かい実用的なところまでを網羅的に聞けた
なお、研修にご参加いただいた方には、Hakuhodo DY ONEオリジナルのプロンプト(訴求軸提案プロンプト、広告キャンペーン提案プロンプト、広告文作成プロンプトなど)を提供しています!プロンプトの中身(案件の概要や要件など)を書き換えるだけで、すぐに業務へ活用いただける内容となっています。
さらに、研修後においてもHakuhodo DY ONEの専門コンサルタントが1on1フォローを実施、実業務における生成AI活用課題へのアドバイスも行い、生成AIの業務への活用をサポートします。
まとめ
Hakuhodo DY ONEの『生成AI BootCamp』は、生成AIの基礎知識から実践的なプロンプト作成、そして実務での活用イメージまでを網羅した研修プログラムです。 本研修を受講することで、生成AIの基礎を理解し、簡単なプロンプトを作成できるようになり、自身の業務における生成AI活用のイメージを具体的に持っていいただけます。
今回実施した『生成AI BootCamp』は、先行案内として限られた企業様を対象に実施しましたが、大変ご好評をいただきましたので、今後正式にリリースを予定しています!
AIコンサルティングの専門チームが、実業務の中で生成AI活用が「当たり前」になるようサポートしますので、『生成AI BootCamp』にご興味のある方、「生成AIを業務で使いたいけれど、どう活用すればいいか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください!