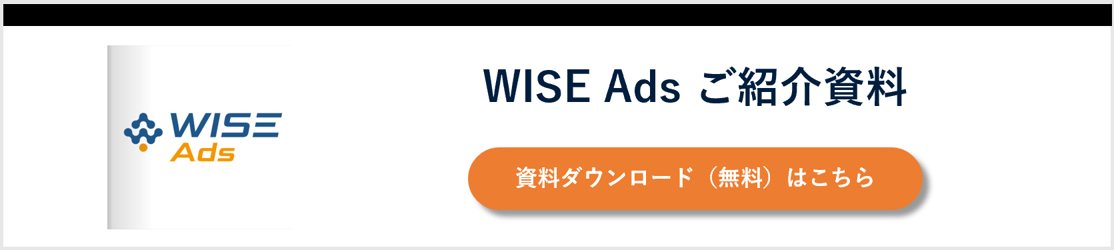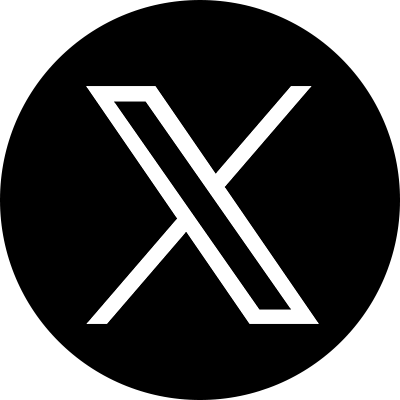デジタル広告は、現代のマーケティングにおいて不可欠なツールとなりました。膨大なデータを処理するさまざまなプラットフォームの登場により、特に、広告の最適化を自動的かつ即時的におこなう運用型広告は、現在の広告配信において欠かせない要素の一つです。
しかし、その利便性の一方で、企業のブランドを毀損するリスクが潜んでいることをご存知でしょうか?
「思わぬ場所に広告が掲載されてしまった」
「不適切なコンテンツと並んで表示されてしまった」
といった事態は、企業の信頼を揺るがし、ビジネスに大きな損害をもたらす可能性があります。
本記事では、昨今のデジタル広告市場におけるブランド毀損のリスクとその具体的な対策について、総務省が2025年6月に発表したガイドライン(※1)の内容も踏まえながら解説します。
そして、Hakuhodo DY ONEがこれらのリスクとどのように向き合い、企業のブランドを守り、広告効果を最大化するのかを紹介します。
(※1)参考:総務省、「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」、総務省ホームページ
昨今のデジタル広告市場、運用型広告の課題
1-1. 生活者の行動変容とデジタル広告市場の拡大がもたらすブランド毀損リスク
デジタル広告の台頭には、生活者の消費行動の変化が大きく影響しています。スマートフォンやSNSの普及により、生活者は情報収集や購買をインターネット上でおこなうようになり、デジタルメディアの接触時間が長くなりました。企業はこの変化に対応するため、多様な媒体へ瞬時に自動で広告配信が可能な、運用型広告をはじめとするデジタル広告への投資を加速させています。
しかし、広告配信の自動化・最適化が進む一方で、広告がどこに、どのような文脈で表示されるのかを完全にコントロールすることが難しくなっています。以下に二つの実態を紹介します。
実態①:配信経路の複雑化と不透明性
従来のいわゆるマス媒体(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)の広告取引では、広告主・広告会社・媒体という限られた主体間で完結するケースが一般的でした。
しかし、デジタル広告の運用型広告においては、その利便性を追求するために、広告が実際に媒体に配信されるまでに、さまざまなプラットフォーム事業者や関係主体が介在しています。これにより、広告主は広告枠を指定せず自由に大量に取引ができる反面、自らの広告がどのような媒体やコンテンツのそばに表示されているかを、広告主が十分に把握しきれないという不透明性が生じています。悪意を持った事業者がこの経路に入り込む可能性も否定できません。

実態②:配信先の多様化と質の悪化
デジタル広告の配信先は、その種類も多様化しています。キュレーションサイトのようにさまざまな情報元が混在する媒体や、ユーザー生成コンテンツ(UGC)と呼ばれる、不特定多数の一般ユーザーが投稿したコンテンツを掲載する媒体の広告枠も、現在では配信先として多くを占めています。生成AIの進化により、これらの媒体での発信が容易になった一方で、こうした技術をフェイクニュースやヘイトスピーチといった悪質・不適切なコンテンツの生成に利用する悪意を持ったユーザーも現れているのが現状です。また、MFA(Made-for-Advertising)サイトと呼ばれる、低品質なコンテンツと高い広告比率を占めるWebサイトも存在し、これらはデジタル広告収益を得ることだけを目的に運営されています。
1-2. これらの実態が企業にもたらす具体的な損害
上記の実態を十分に理解せず広告配信をおこなってしまうと、偽情報や違法コンテンツへの広告掲載によるブランドイメージの低下や、意図していない媒体やbotに広告が掲載され、広告費が不正に流出してしまうといったさまざまなリスクが生じます。
具体的に説明しましょう。
① 企業イメージの低下(ブランド毀損)と信頼の喪失
違法・不当なサイトや、不適切なページに掲載されることにより、生活者は企業に対して不信感を抱き、ブランドイメージが大きく損なわれます。近年は特に、広告主が意図しない媒体に広告が配信されていることがSNS等で拡散され、イメージ悪化を助長するケースも多発しています。顧客離れや売上の減少、株価への影響、生活者や株主からの訴訟リスクなど、コンプライアンス遵守が強く問われる昨今において、その影響範囲は広大です。
2017 年には、大手動画サイトで、国際的な過激派組織に関連する動画に多くの企業の広告が表示されていることが問題となりました。(※2)企業のブランドイメージを毀損するだけでなく、動画を制作・発信した反社会的な団体に広告収入をもたらす可能性があるため、多くの広告主がそのサイトへの広告配信を一時的に取りやめる事態となりました。
(※2)参考:リンクタイズ株式会社、「世界最大級の広告代理店がユーチューブから撤退 悪質動画に反発」、Forbes JAPAN
② アドフラウドにより広告費が流出するリスク
アドフラウドとは、botを利用したりスパムコンテンツを大量に生成したりすることで、本来カウントすべきではないインプレッションやクリック等の無効なトラフィックを不正に発生させ、広告費を詐取する行為のことです。もちろん、広告効果計測のための自動化プログラムなども存在するため、一概にbot全てが悪質というわけではありません。しかし、こうした技術を悪用して不当な広告収入を得ようとする事業者がいるのも事実です。このような不正な媒体に流れてしまった広告予算は、認知向上やコンバージョン獲得といった本来の広告配信の目的にはまったく貢献せず、無駄な費用となってしまいます。
③ デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク
広告費の流出は、単なる経済的損失に留まりません。その流出先が、偽情報・誤情報を拡散する悪質な事業者、あるいは違法なコンテンツを掲載する媒体の資金源になるという側面も理解しておく必要があります。業界団体からは、こうした資金が社会に悪影響を及ぼす可能性があると警鐘が鳴らされています。(※3)このような反社会勢力への広告費の流出を、企業として防がなければなりません。
また、このような媒体への広告配信は、悪質な事業者に金銭的メリットを与えているだけでなく、本来の権利者に報酬が支払われないという不健全な事態にも繋がります。さらに、生活者からは「あの企業は違法コンテンツを容認している」とみなされ、結果としてブランド毀損の要因にもなり得ます。

こうしたデジタル広告特有のリスクに対し、総務省は、インターネット広告における透明性や健全性の確保について、たびたび注意喚起をおこなっています。特に今回のガイドラインでは、広告主に対し、広告掲載面の選定における注意義務や、ブランドセーフティの確保に向けた取り組みの重要性を強調し、そこに広告主や団体の経営層も関与する必要があると強く推奨しています。これらの指針は、デジタル広告運用におけるブランド毀損リスクへの対策が、もはや単なる「推奨」ではなく「必須」の課題であることを示唆しています。
デジタル広告の健全な発展のためには、広告主が「①企業イメージの低下(ブランド毀損)と信頼の喪失」、「② アドフラウドにより広告費が流出するリスク」、「③ デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク」を正しく認識し、適切な対策を講じることが不可欠です。
次章では、具体的な対策について解説します。
(※3)参考:経済産業省、「経営層も知っておくべきデジタル広告の「買い方改革」の必要性~デジタル広告取引の健全化について、広告主・広告代理店・媒体社・行政機関が語る~に関するオンラインセミナー」、経済産業省ウェブサイト
ブランド毀損を防ぐための具体的な対策
2-1. 「ブランドセーフティ」と「ブランドスータビリティ」の重要性
ブランド毀損を防ぐためには、「ブランドセーフティ」と「ブランドスータビリティ」という2つの概念を理解し、実践することが重要です。
■ブランドセーフティ(Brand Safety):
広告がヘイトスピーチ、暴力、アダルトコンテンツ、フェイクニュースなどの「不適切」と判断されるコンテンツの隣に表示されないように保護することです。広告主のブランドイメージを損なう可能性のある、明確に有害なコンテンツからの保護を目的とします。

■ブランドスータビリティ(Brand Suitability):
ブランドセーフティよりもさらに踏み込み、広告主のブランドイメージや価値観に「適合する」コンテンツの隣に広告が掲載されるようにすることです。
例えばアルコール飲料を扱うブランドの出稿先として、子育て関連メディアへの出稿はネガティブな関連性を想起させかねません。一方で、ファミリーカーを扱う自動車ブランドであれば、同じ子育て関連メディアでも出稿によって実際の利用シーンを想起させ、購買意欲を効果的に高めることが期待できます。
このように、ブランドに適合する掲載面は、ブランドの個性やターゲット層によって異なるため、より細かく掲載面をコントロールするという考え方が「ブランドスータビリティ」です。

2-2. アドベリフィケーションツールの活用
前章1-2.で述べたような広告主のリスクを排除し、ブランド保護を実現するための第一歩として、アドベリフィケーションツールの活用が不可欠です。アドベリフィケーションツールは、広告が不適切なコンテンツに配信されるのを除外・制御し、広告が実際にどこに表示されたか、そのコンテンツは適切だったか、広告詐欺はなかったかなどを検証し、レポートを提供します。これにより広告主は、自社の広告が意図した通りに表示されているかを確認し、ブランド毀損のリスクを低減することができます。
主なアドベリフィケーション提供事業者には、DoubleVerify、Integral Ad Science(IAS)、Momentum、Spider Labsなどがあります。中でもDoubleVerifyは、AIと機械学習を駆使し、膨大なウェブサイトやアプリのコンテンツを分析します。ブランドセーフティ基準に違反するコンテンツや、広告主のブランド適合性基準に合致しないコンテンツを特定し、広告配信をブロックします。これにより、広告主は意図しない場所に広告が掲載されるリスクを大幅に低減できます。
このようなアドベリフィケーションツールの活用は、ブランド毀損や広告費流出、そして不健全なエコシステムへの加担といった広告主の主要な課題を効果的に解決します。
不適切な広告掲載面を排除することで、「①企業イメージの低下(ブランド毀損)と信頼の喪失」を未然に防ぎ、不正なインプレッションやクリックを検出・遮断することで「②アドフラウドによる広告費の流出」を阻止します。さらに、広告配信の透明性と健全性を確保することにより、「③デジタル社会の不健全なエコシステムへの加担」を回避し、健全な広告市場の発展に貢献することができるのです。
2-3. その他の効果的な対策
アドベリフィケーションツールの活用に加え、以下の対策も効果的とされています。
■品質認証事業者との取引
JICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)などに認証された事業者との取引は、広告の品質と透明性を担保する上で非常に有効です。JICDAQは、デジタル広告の品質に関する基準を設け、その基準を満たす事業者を認証することで、広告主が安心して取引できる環境を提供しています。認証事業者との取引は、アドフラウドやブランド毀損のリスクを低減し、より健全な広告運用に繋がります。
■配信先の取捨選択
広告の掲載面をコントロールするためには、以下の手法が有効です。
- ホワイトリスト・ブラックリストの活用:
広告を掲載したい優良な媒体をリストアップする「ホワイトリスト」や、掲載を避けたい不適切な媒体をリストアップする「ブラックリスト」を活用し、配信面を細かくコントロールします。

- 純広告やPMP(Private Marketplace)などの活用:
特定の媒体や限られた配信先に広告枠を買い付ける「純広告」や、特定の広告主に対して限定された広告枠を提供する「PMP」といった手法を用いることで、配信先を厳選し、ブランド毀損のリスクを極めて低く抑えることができます。ただし、これらの手法は配信先をかなり絞るため、リーチ数やインプレッション数が限定される可能性がある点に注意が必要です。

※画像引用:株式会社プラットフォーム・ワン、PRODUCTページ「YieldOne®」、プラットフォーム・ワンコーポレートサイト
Hakuhodo DY ONEの取組み
– 独自の広告配信サービスを活用した「WISE Ads Brand Suitability」
デジタル広告におけるブランド毀損リスクへの対策は、企業にとって喫緊の課題です。
Hakuhodo DY ONEは、総務省のガイドラインに沿い、広告主が安心安全な広告配信を行えるよう全面的にサポートします。
その一つの手段として、当社の広告配信サービス「WISE Ads」を活用した「WISE Ads Brand Suitability(ワイズアズ・ブランドスータビリティ)」を提供します。

このソリューションは、アドベリフィケーションツールを提供するDoubleVerifyと提携し、その最先端の技術とHakuhodo DY ONEが培った媒体社との強固なネットワークや知見を掛け合わせることで、高度なブランドスータビリティを実現し、広告主のメッセージやイメージをより高めることを目指します。
■DoubleVerifyとの連携による高精度なブランド保護
「WISE Ads Brand Suitability」は、業界トップクラスのアドベリフィケーションツールであるDoubleVerifyと強固に連携しています。ヘイトスピーチや暴力的なコンテンツからのブランドセーフティはもちろん、広告主のブランドイメージにそぐわないコンテンツへの掲載も徹底的に排除します。さらに、アドフラウド(広告詐欺)の検出・防止機能も搭載しており、不正なインプレッションやクリックによる広告費の無駄を排除し、広告予算を有効活用できます。

■多様な配信面への掲載
「WISE Ads Brand Suitability」は、DoubleVerifyによる高精度なブランドセーフティを実現しながらも、多様な媒体への広告配信を可能にします。またブランドスータビリティを体現すべく、広告主や案件に最適な配信面を選定します。これにより、ブランド毀損リスクを抑えつつ、広範なユーザー層にリーチすることが可能です。また、十分なインプレッション数を確保できる配信設計によって、広告の露出機会を損なうことなく、ブランド認知度向上に貢献します。

※参考:Hakuhodo DY ONE、「Hakuhodo DY ONEの広告配信サービス『WISE Ads」にDoubleVerifyのソリューションを標準搭載〜広告の品質・透明性・効果を測定・保証するためのブランドセーフティ・ブランドスータビリティ(適合性)を考慮した配信を実現〜」、2025年5月9日
おわりに
デジタル広告は、企業にとって強力なマーケティングツールであると同時に、ブランド毀損というリスクを内包しています。しかし、適切な対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑え、広告効果を最大化することが可能です。
Hakuhodo DY ONEが提供する「WISE Ads Brand Suitability」は、DoubleVerifyとの連携による高度なブランド保護と、効率的な広告配信を両立させることで、企業のデジタルマーケティングを強力に支援します。
ブランド価値を守り、ビジネス成長を加速させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
※本記事の挿入画像の一部は生成AI(Adobe Firefly)を利用して作成しています。